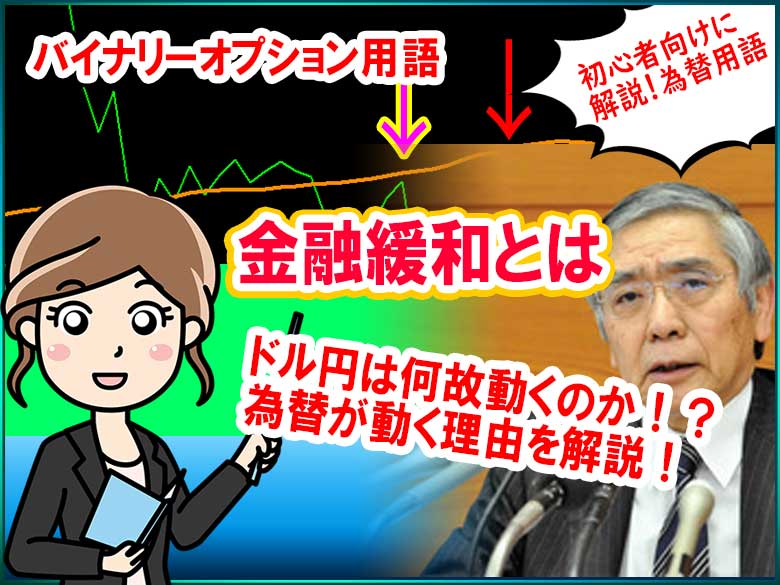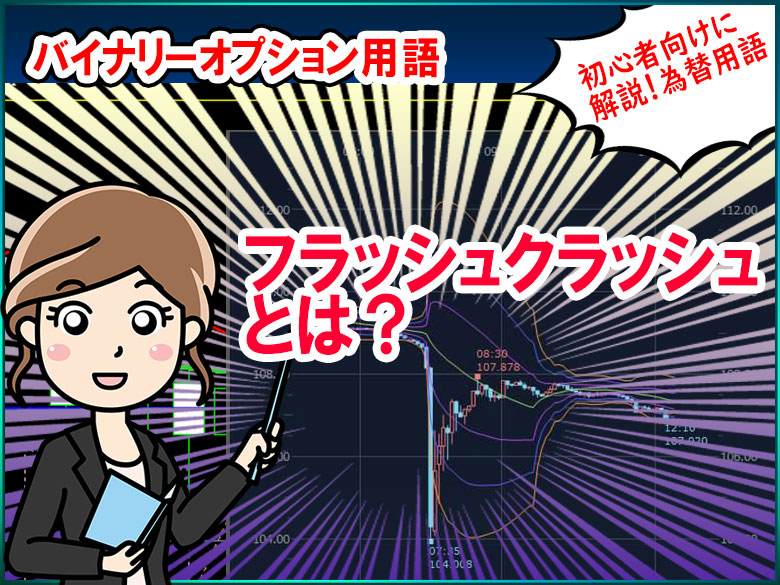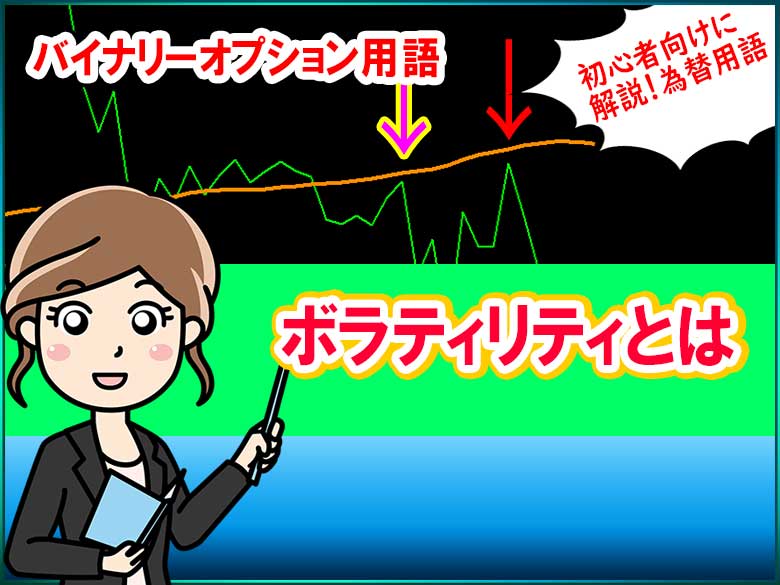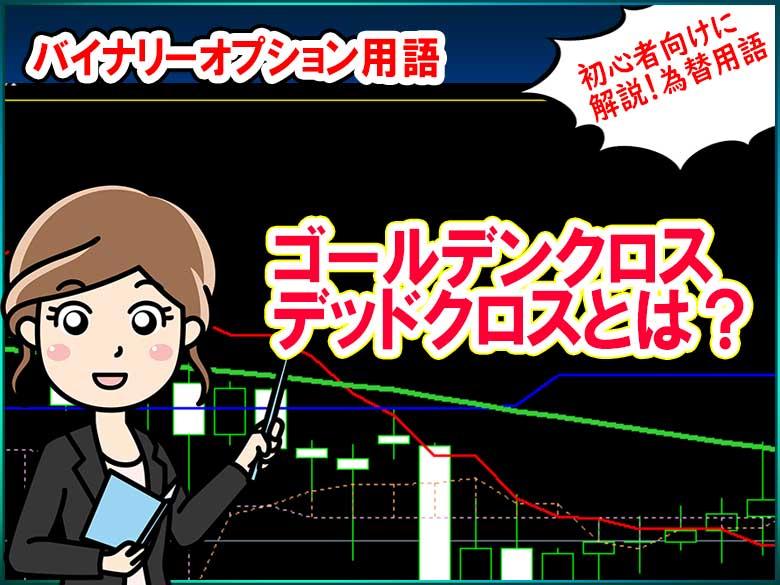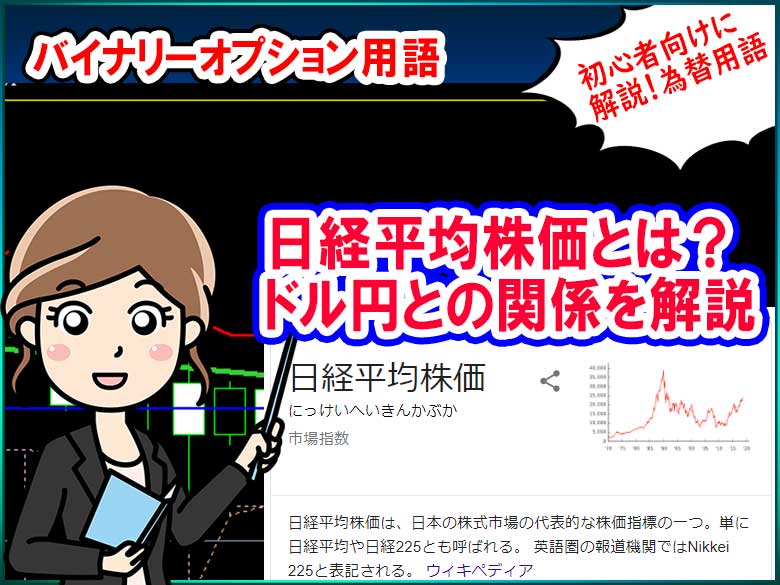「FOMCの利上げ」「アメリカが利下げ」等と、ドル円の上昇を左右するワードとして欠かせないのが利上げ・利下げです。
2019年まではアメリカは利上げという政策をしてきましたが、2020年のコロナショックにより今度は利下げというワードが出てきました。
利上げとは何か利下げとは?を解説していきます。
FOMCや、FRBや、政策金利といった言葉も解説します。
利上げとは
利上げとは、各国中央銀行が政策金利を引き上げることをいいます。
日本で言えば「日本銀行」が、米国で言えば「FRB(アメリカの中央銀行)」が政策金利を引き上げる事を指します。
政策金利とは
では「政策金利」とはなんでしょうか?
政策金利とは、中央銀行が一般の銀行にお金を貸し出す際の金利のことです。
銀行に銀行がお金貸すという表現が日常生活ではピンと来ないという方もいらっしゃるでしょう。
よく知ってるUFJや、りそなは一般の人が使う銀行で、それらの銀行が取引する銀行が、中央銀行といったイメージです。
金利というのは身近な用語でいえば、「利息」という風に考えてよいでしょう。
ドラマや映画で、町工場や企業が何か新しい事業をしようとして、必死に銀行から融資(お金を貸りる事)を頼むシーンが沢山あるのでこれを思い出すとイメージしやすいでしょうか? 例えば大ヒットした「半沢直樹」とか。
お金を借りたら利息が発生します。 借りたお金で新しい事業を始めて儲かったら、借りたお金よりも少し上乗せして返します。
この利息を上げるのが利上げ。 下げるのが利下げです。
利上げ・利下げのメリットとデメリット
利上げに関してのメリットは、逆から考えていった方が分かりやすいです。
つまり、利下げの逆という説明の方が分かりやすいのでまずは利下げのメリットから説明します。
利下げのメリット
利下げは、政策金利を引き下げることによって、金融機関が安い金利でお金を調達でき、企業は安い金利でお金を借りることができます。
企業は安い金利でお金を調達し、設備投資など(個人で言えば、住宅購入など)を行い、世の中の経済が活発に動くようになります。 これによって景気がよくなります。
また、個人も安い金利で銀行にお金を置いておいても意味がないので、投資しようと株や、金利の高い商品、金利の高い外貨などに投資しようとします。
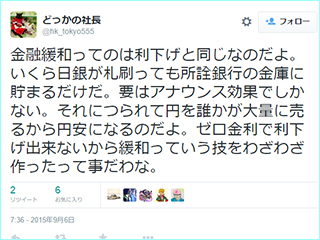
もっと乱暴に言えば、お金を市場にばらまけば、人はそのお金を物に変えたりサービスを受けようとします。 沢山物が売れてお金が入ってそれをまた他所で使うから景気が良い状態が生まれます。
景気対策として、お金を増やして市場にばら撒くのは一つの手なのです。
利上げのメリット
一方、利上げは利下げの逆です。
利下げ効果により、経済活動が活発に動き、景気が良くなると、人の購買意欲も上がり、資源も含め、物を必要とする人が増えるため、物の値段が上昇していきます。その一方で、安い金利でお金を世の中に流し続ければ、その通貨の価値はどんどんと下がっていきます。
例えばバブルの状態で1ドルの商品を円で買おうとしたとき、「私は115円出します」「金ならあるんだ。120円出すぜ」「金ならある、125円出すよ」「金ならある、200円出す」と、どんどん物の価値が下がっていきます。
極端な話をすれば、やり過ぎたら福沢諭吉が紙屑になってしまいます。 例えば、老後の為にと母親が貯金しておいた3,000万円・・これが紙くずになってしまうのです。
これがインフレ(ハイパーインフレ)です。
この過度なインフレ状態を防ぐために各国中央銀行は、利上げを行おうとします。
すると、今度は企業は少し投資に慎重になったり、個人であれば、預貯金にお金を預けるようになり、世の中からお金の流通量が減る効果があります。
アメリカは景気対策で利下げを今までしていてので、正常に戻すべく利下げを段階的に行っていくという政策局面に入っているのです。 急にやると景気がヤバくなるのは分かっているので、指標発表などで景気が良いのを受けて慎重にやっていくよというのが2016年~2017年現在の話。
為替が動く理由(ドル円を例に)
では、例えばアメリカが利上げをするとドル円が上昇するのは何故でしょうか? 実はとても簡単な話です。
アメリカが利上げをすればドル(お金)が市場に回らなくなる=ドルの価値が上がるという事です。
沢山物が溢れればその物の価値が下がり、希少な物は価値が上がるのと同じです。
ドルが上がればドル円は上昇します。
先ほど逆に考えましたが、「利下げ(金融緩和)」でドルの価値が下がると分かっていれば、既に持っているドルを別の「物」や「円」に替えておこうと考えるのです。
2017年の3月段階ではトランプ相場でアメリカの株も上昇して景気も良好なので利上げ4回あるんじゃないか?という期待で上昇があり、3回だという声明で一気に下がりました。
利上げや利下げは、為替の価値を変動させる何よりも直接的な理由なので、大きく変動する理由となるのです。
日本では利下げを金融緩和と表現する
日本では日銀黒田総裁・アベノミクスがかかげる政策として金融緩和という表現をしますが、これは利下げという風に捉えておくと理解しやすいでしょう。
アメリカを例に学ぶ利上げ・利下げ
アメリカを例に挙げて解説します。
リーマンショックのあと、アメリカは金融緩和を行いました。(金融緩和=利下げ)
リーマンショックによって大打撃をうけた景気を回復させることを目的に、お金の巡りをよくしようとしました。
政府が銀行を救って立て直すために金利を下げて(利下げ)、銀行に、そして世間にお金が回っていくようにしました。
そうした結果、人々は再びお金を借りて高価なモノを買えるようになって、住宅価格などの物価は上昇しました。雇用も回復しました。景気が回復したように見えました。みなさんも、アメリカの景気が回復したというニュース、聞いたことがあると思います。
下げた金利は0に近く、「ゼロ金利政策」という言葉も日本でも最近ありました。
しかし、金利がゼロ近いということは異常なことです。異常な状態からは早く元に戻したいものです。
景気が回復したのなら、そろそろ普通の状態に戻してもよいのではないか、と考えられて、そしてそれがもうすぐ戻されようとしているのです。 それが利上げです。
現在のアメリカは、アメリカ国内の景気のことを考える(自分の国のことだけ考える)と、利上げはせざるを得ない状況なのです。
でも、利上げすると、世界経済に打撃を与えることになることは、世界中で懸念されています。(以下でさらに詳しく解説)
アメリカもそのことは知っているので、どちらを取るべきかが難しい問題なのです。世界経済への影響のことを考えて「利上げしない」という選択をすると、せっかく回復基調だったアメリカ国内の景気がまた下向きになってしまうことにつながります。
ちなみに、日本はアベノミクスでそれを真似しています。黒田総裁が金融緩和を打ち上げて、ゼロ金利も発表しました。
2020年、コロナショックで利下げ発言
2019年まではアメリカは金融緩和によって経済が回るようになったので利上げ戦略中、日本は遅れてアメリカの真似をし始めたので、利下げ中だったので、大きくドル円は上昇傾向にありました。(金利差により、円をドルに替えた方が得という現象がおきています)
2020年3月に、コロナウィルスがアジアだけの問題でなく欧米にも広がった事で現在世界的な景気悪化が懸念されています。 そこでアメリカからも利下げ発言が出ました。
逆に考えれば0金利、マイナス金利のままならこの政策が出せなかった事になりますから、段階を踏んで利上げをしていったアメリカの政策は正解だったという事になります。
他国にまで米国利上げが影響を与える理由
今まで書いた通り、基本的には、利上げ・利下げというものは、各国の政策によるもので、それぞれ国の情勢により行われることなので、他の国が騒ぐことではありません。
では、何故米国の利上げにそれほど関心が集まるのでしょうか?
先ほど少しふれた点にはなりますが、利下げによりお金が借りやすくなり、お金が世の中にまわりやすくなります。
現在はグローバル経済ですから、米国の企業も海外に積極的に投資を行います。また、金利の安い米ドルを調達して、金利の高い新興国などへも投資を行います。これによって、新興国にお金が回り、経済が発展します。また、新興国の多くは資源国でもあることが多いため、米国をはじめ世界的に経済が良くなれば、資源を積極的に輸出し、資源価格も上昇します。そして新興国のGDPも上昇するわけです。
ただ、新興国への投資は金利が高いというメリットもありますが、それだけリスクも高いという面も持ち合わせています。
米国が利上げを行うと、企業は投資に慎重になるのは先の通りです。企業活動の積極性が緩やかになると、資源の利用も減るわけですから、資源に余剰が発生し、資源価格が安くなります。新興国の成長は鈍り、新興国の人々へも影響がでてきます。またリスクの高い新興国への投資よりも、格付けの高い米国債への投資への移行など、新興国から資金が逆流し始める懸念もあるわけです。
また、新興国によってはドルペッグ制っていうんですけど、自分の国の通貨をドルに連動させている国もあります。 「世界基準のドル」に変動を合わせておけばいろいろ安心みたいなイメージですかね。 日本がもしそうだとしたら、アメリカでジュースが100円だったのが急に1000円になったら、日本もジュースが1000円になるみたいな。 日本だけ100円のままだったらこっちに殺到して大変な事になりそう。
米国が利上げをすると、自国通貨も上昇してしまうような国もあります。経済が下降気味になる国の通貨の価値が上昇するわけですから、困った問題です。また、実際に資金が逃避し始めると、逃避を食い止めるため、さらに利上げをして、海外の資金が逃げないように試みたりする国もあります。
1994年のメキシコ危機は、海外から資金が流入し、好調な経済だったメキシコが、米国の利上げをきっかけに、資金がメキシコから逃避したことがきっかけでした。その後も、ロシア、アルゼンチン、ブラジルなど、米国の利上げをきっかけに、経済が落ち込んだ例があるため、今回も新興国への影響が懸念されています。
また、現在は新興国がヨーロッパとかアメリカとか日本にとって、大きな市場になっていることから、新興国が落ち込むと先進国にも影響が出ることが予想され、さらに米国の利上げが世界に与える影響が高いのではないかと思われています。
用語補足
FRBとは
FRBとは、アメリカの中央銀行・日本でいう日本銀行(日銀)と同じです。
FOMCとは?
「FOMC」とは、FRBの理事7名と地区ごとの連邦準備銀行総裁5名で構成されている、アメリカの金融政策を決定する最高意思決定機関のことです。